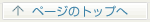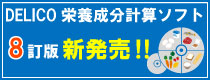AIによる業務効率化について
師走の声も聞こえ始める10月。
そろそろ忙しい時期に差しかかっている方も多いのではないでしょうか。
当社では、10月15日より「食品開発展2025」に出展いたします。
その出展担当として、私も慌ただしい日々を過ごしております。
そんな中、メールマガジンの執筆当番が回ってきました。
「業務の効率化はどこまで可能なのか?」というテーマのもと、今回はAIをフル活用してみることにしました。
デリコとして、食品全般に関する質問をAIに投げかけてみました。
質問1)2025年度上半期の食品に関する流行を400字程度にまとめて記載して
COPILOTの回答)
2025年度上半期の食品トレンドは、物価高騰やタイパ志向を背景に「手軽さ」と「やみつき感」がキーワードとなりました。
特に人気を集めたのは、旨だれに漬け込む「夢中〇〇」レシピや、価格安定と調理の簡便さから注目された「カット野菜」。
また、蒸し調理の利便性が評価され「せいろ」やフライパンでの同時蒸し調理も話題に。
SNSでは「ドバイチョコ」などASMR効果のある食感系スイーツが流行し、節約食材を使った「ちくわおかず」も人気を博しました。
さらに、ビールやRTD飲料では「苦味」が新たな魅力として支持され、アウトドア調味料や粉末化商品もヒット。
全体として、食の楽しさと効率性を両立するアイデア商品が消費者の心をつかんだ半年でした。
GEMINIの回答)
2025年度上半期は、物価高や健康志向の高まりを背景とした食のトレンドが顕著になりました。
まず、天候不順や輸送コスト上昇による「野菜の価格高騰」が大きな話題となり、フーディストサービスによる
「2025年上半期トレンド料理ワード」では大賞に選ばれました。これに対応する形で、比較的価格が安定している「カット野菜」や、
安価な食材でかさ増しするレシピが人気を集めました。
また、手軽に本格的な味が楽しめる「夢中〇〇(無限漬け)」や、ほったらかし調理で「タイパ(タイムパフォーマンス)」に優れる
「せいろ蒸し」がトレンド入り。料理のプロセス自体を楽しむ「プロパ(プロセスパフォーマンス)」も注目され、
調理の簡便性と満足感の両立が求められました。
さらに、腸活や高タンパク食品への関心も高く、健康を意識した食品のニーズが拡大しています。スイーツでは
「グリークヨーグルト」や、韓国発の「じゃがいもパン」、独自に進化した定番スイーツが若年層を中心に流行しました。
考察)
全体的に、具体的な事例がやや古く感じるのは、食品業界の人間として常に先を見ているからかもしれません。
こうした近過去のまとめは、事例が多くなければ引用されにくいため、情報が陳腐化してしまうのは当然とも言えます。
ただし、「夢中〇〇」や「せいろ蒸し」など、両者に共通して登場する項目は、2025年上半期の実際の流行として参考にしてよいでしょう。
なお、話題となった「米の件」が含まれていないのは、上半期の分析だからかもしれません。
通期であれば「備蓄米」などのキーワードが出てくる可能性もあるはずですが、こういった時代背景も
正確に示すのはAIの良さなのではないでしょうか。
質問2)2026年に食品の流行予測を400字程度にまとめて
COPILOTの回答)
2026年の食品トレンドは「ウェルビーイング」と「サステナブル」が中心軸となりそうです。健康志向の高まりにより、
腸活・免疫ケア・メンタルヘルスを意識した機能性食品が注目され、特に高齢者や単身世帯向けの栄養バランス食が
拡充される見込みです。また、地元産食材やアップサイクル食品など、環境配慮型の商品が支持を集め、
エシカル消費が定着しつつあります。デジタル技術の進化により、AIによるパーソナライズ提案やオンライン販売の
利便性も向上。さらに、猛暑や災害への備えとして、保存性・簡便性に優れた食品の需要も高まるでしょう。
全体として、身体と心の健康、環境との共生、そして生活防衛を意識した「賢い食選び」が2026年のキーワードとなりそうです。
GEMINIの回答)
2026年の食品業界では、物価高や猛暑といった社会・環境の変化に対応した食のトレンドがさらに加速すると予測されます。
具体的には、物価高を背景に、安価な野菜などを利用してかさ増しする「ましましベジ」や、フードロス削減に
貢献する「なごりフルーツ」などが注目を集めるでしょう。また、地球温暖化による猛暑に対応した、
猛暑の気候でこそ美味しく育つ「猛暑順応ベジ」など、気候変動を逆手に取った新しい食材も登場すると見られます。
さらに、健康志向の高まりから、腸内環境を整える根菜類を簡単に取り入れられる商品や、高栄養価の野菜へのニーズも高まるでしょう。
また、代替肉などのフードテック分野も成長を続け、日本では2026年を目処に培養肉の販売が本格化する可能性も
指摘されています。消費者は、単に美味しいだけでなく、環境や健康、社会課題の解決に貢献する
「サステナブル」な食品をより一層重視するようになるでしょう。
考察)
AIの回答は、メディアによる流行予測と比べると、事象予測が中心で、具体的な「食品」の提示が少ない印象です。
これはメディアが、純粋な流行予測だけではなく、『来年○○を流行させたい』という意図や、誘導を含んでいる部分も
あるのではないでしょうか。個人的には事象予測を並べる『AIの予測』より、
意図が介在しようと、具体的な『食品事例を提示しているような予測』の方が、
面白いと感じてしまいますし、自分が行うのならば、こちらの都合の良い意図を
大きく介在させて、流行予測を出すだろうと想像しました。
※作成者の意図を込めない、事実だけを並べて予測する。というのがAIの良さではあるので、
どちらが正しいとは一概に言えません。
いかがでしょうか?
AIの回答がすべてのトレンドを網羅しているわけではありませんが、的を射た内容も多く、まとめとしては十分に活用できるレベルです。
数多くの事例を把握する手段としても有効であり、少し手を加えることで、十分にベースとして活用できるのではないでしょうか。
ちなみに、ここまでの作業時間は約10分。
これまでメールマガジンの作成に1時間ほどかかっていたことを考えると、
内容はともかく、時間短縮の効果は絶大です。
ここで終わっても良いのですが、もう一つ是非おすすめな「AI」が最近出てきました。
それがGeminiの画像生成・編集AIモデルである、通称『Nano Banana』です。
AIで画像生成・編集をやられたことが有る方なら共感していただけると思いますが、これがかなり使えます。
今まで、AIで簡単な画像生成を行った場合、右手と左手が逆になっていたり、机の脚が1本無かったりと詳細なところで、
ミスが多く、又、それをAIに修正してもらうのが、一苦労だったのですが、Nano Bnanaですとそういったミスも少なく画像生成もできますし、
さらに他のAIで作成した画像も簡単な指令で的確に修正してくれます。他にも便利に使えたり、
さらに容易に画像生成ができたりと良くなった部分はたくさんあるのですが、
ここは実際に『Nano Banana』の良さをAIに聞いてみてください。的確に答えてくれると思いますよ。